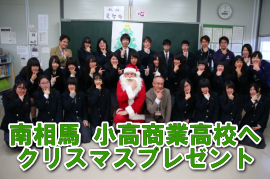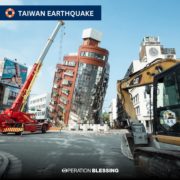【東日本大震災】3.11から3年 東北と私たちの3年間
震災発生直後の緊急支援活動 2011年3月-4月
東日本大震災の発生を知ったオペレーション・ブレッシング・インターナショナル(OBI)のアメリカ本部は、
2011年3月12日午前6時に、埼玉県在住のドナルド・トムソン(現オペレーション・ブレッシング・ジャパン代表理事)に被災地支援について依頼の電話をしました。
トムソンはOBI本部の国際災害部長のディビッド・ダーグ氏とともに震災発生72時間後には被災地で緊急物資配送を開始しました。
私たちのミッションは、迅速に行動し、被災者の方々の苦痛を和らげ、希望を届けることです。
OBIの30年以上にわたり世界各地で支援を行ってきた経験を元に、すみやかに緊急支援活動を実践しました。
2011年3月15日~ 被災地に入る
; ?>/images/311/photo02.png” /><br />
</p>
<p>塩竈市に入りワゴン車に積めるだけの物資を持っていきました。避難者に緊急物資、米、水、パン、果物、暖かい衣類、調理用ストーブ、ろうそく、缶詰食品等です。</p>
<p>メインの体育館では、数百人程度が体育館の床で寝泊まりしており、いつまでこの状態でいるのかが分からない不確かな状況で暮らしていました。</p>
<p>震災後初めて、私たちは一息入れ、避難所の家族の方々と話をする時間をもつ事が出来ました。</p>
<p class=)
; ?>/images/311/photo20.png” /></p>
<p class=) その中で私たちの注意を引いたのは、松本さん一家でした。3歳になる双子の男の子カシン君とミハヤ君は、体育館の中を元気に走り回っていました。
その中で私たちの注意を引いたのは、松本さん一家でした。3歳になる双子の男の子カシン君とミハヤ君は、体育館の中を元気に走り回っていました。
ご主人の松本さんにお話を伺うと、津波により家の一階が完全に泥で埋まったことを語ってくれました。
松本さん一家は所持品のほとんどを失い、再び家に住むことは不可能との事です。
後どのくらい家族全員(妻、祖母、3人の子どもを含む6人)が避難所に住むことになるのか分からない
と説明する松本さんは、やや困惑した表情を見せてました。
彼は食料や水を供給した私たちに、こんな状況下にも関わらず大変よく世話をしてもらって感謝している
と話してくださいました。
ご自身が大変な状況にも関わらず、私たちを気遣ってくださった事は今でも忘れられません。
; ?>/images/311/photo21.png” /></p>
<p class=) また、OBIチームは塩竈におもちゃも持って行ったので、ヨーヨー、サッカーボール、ヘリコプターを渡すと、松本さんの双子の男の子は非常に喜んでいました。
また、OBIチームは塩竈におもちゃも持って行ったので、ヨーヨー、サッカーボール、ヘリコプターを渡すと、松本さんの双子の男の子は非常に喜んでいました。
緊急支援を実施するにあたり、様々な方のご協力がありました。
例えば、会社を経営しているサクラさんは、配送でOBIのチームに参加して車両と燃料を供給してくださり、非常に助かりました。
; ?>/images/311/photo22.png” /></p>
<p>彼は東京を出発する前に、被災者にとって役に立つと思われる物資をいくつか集めてくれました。<br />
塩竈でトラックの荷下ろしをしていると、サクラさんのアシスタントの方が大きな傘の束を下ろしているのを見ました。<br />
傘のような当たり前のような物でも、全てを失った家族にとっては大切なものなのです。</p>
<p><img alt=)
; ?>/images/311/photo03.png” /></p>
<p>石巻市の総合病院では多くの患者が出入りし、廊下にもベッドが並んでいました。<br />
多くの被災者が災害時にその薬を失い、全体的な緊急医療事態は安定している一方で、未治療の慢性疾患で苦しんでいる患者が増えていました。<br />
500人の患者と多くの職員のための食料と衛生用品を病院の地下に搬入しました。</p>
<div class=)
; ?>/images/311/photo17.png” /></p>
<p>私たちは物資を届けた後、米農家との会合を持つため、そのまま内陸部に向かいました。<strong>被災地では店舗で食品を調達することはほぼ不可能でした。米の需要はとても高く、それを入手できる唯一の方法は、直接農家に行くことでした。</strong></p>
<p>そして翌日には、米を乗せた最初のトラックを石巻市に走らせました。その日聞いたある報告によると、市内の一部では食物がかなり不足しているとの事なので、タイミング的にはちょうど良かったようです。</p>
<p><img alt=)
; ?>/images/311/photo04.png” /></p>
<p>私たちは、被災者1,000世帯が住んでいる大槌町の避難所にも救援物資を届けました。</p>
<p>凍てつくような寒さの中で、被災者に暖かく過ごしてもらうために、当時はお金よりも貴重な灯油と灯油ヒーターを購入し届けました。</p>
<h3>2011年4月~2012年12月 メガネ寄贈</h3>
<p class=)
; ?>/images/311/photo05.png” /></p>
<p>被災地3県の70地区でメガネを失った人に検眼を行った上で、合計4,800個のメガネを寄贈しました。</p>
<p><strong>メガネを受け取った方の笑顔とともに「すごい!見える!」</strong>などの声が所々で聞こえてきました。</p>
<p>他にも<strong>「わぁ!完璧だ!」「はっきり見えたのは一ヶ月ぶりです。」「ありがとうございます。」</strong>などの声をいただいた事は、私たちにとっても大変嬉しいことでした。</p>
<div class=)
宮城県気仙沼市でメガネ寄贈を行った際の映像です。
2011年4月 浦戸諸島に発電機寄贈
浦戸諸島の生活や漁業に必要な電気が不足していて、住民の方々は非常に困っていました。ですが当時の混乱の中で離島に重機を届けるのは困難を極め、荷船操縦者の方や、漁業組合長千葉さんの協力もあって、浦戸諸島にて業務用発電機を浦戸諸島の三つの島へ届けることができました。
; ?>/images/311/photo06.png” /></p>
<p>発電機は野々島の坂の上の避難所と公民館に、寒風沢島では避難所と漁業組合の事務所へと設置され、生活や漁業に必要な電気を提供できました。<br />
<strong>「漁師や島の方々を勇気づけている活動だ」</strong>と言ってくださったのを今でも覚えています。</p>
<h3>緊急支援を終えて</h3>
<div class=)
; ?>/images/311/photo18.png” /></p>
<p>当時の光景について、支援に直接動いたダーグはこう語りました。</p>
<p><strong>「睡眠不足、原発の脅威によるストレス、厳しい寒さ、燃料や物資の欠如、そして震災による破壊の規模、これら全ての要素が重なり、この震災は私が救援活動で関わった災害の中でも最も過酷なものです」</strong></p>
</div>
<p class=) 私たちはこれまでに多くの地震と津波における救援の経験から、長期的なプロジェクトをスタートしました。
私たちはこれまでに多くの地震と津波における救援の経験から、長期的なプロジェクトをスタートしました。
例えば2004年のインドネシアでの津波の際は、緊急の食糧・水・医療の供給の必要がなくなってから漁師の家族のためのボート、避難民のための家屋、そして津波で破壊された沿岸地域における新たな学校や診療所等を作るプロジェクトでした。
東北でもこのような長期的な支援が必要なのは明らかでした。
そのために、オペレーション・ブレッシング・インターナショナル(OBI)は、
日本での活動を担うオペレーション・ブレッシング・ジャパンを発足し、事務所を宮城県富谷町に構えました。
これによって、国内の取り組みを一段と強化することができるようになったのです。
(NPOの認証は2013年3月です。)
漁業を中心とした産業支援 2011年9月-継続中
2011年9月・11月、2012年3月、5月、2013年3月、和船合計90隻寄贈 漁具寄贈
東北3県の産業構造は、自然環境や立地、伝統等の影響から漁業等の第1次産業が多くの割合を占めています。
特に三陸沖~常磐沖にかけての海域は世界3大漁場のひとつに数えられるほどの漁場で、日本の食文化を支えている地域と言っても過言ではありません。
東日本大震災の津波によって、その三陸沿岸部は約500キロにわたり漁産業基盤が壊滅状態となりました。
漁師たちはわずか数分の間に、これまでに築いてきた全てのものを失ったのです。
私たちは漁業組合の皆様からの声を聴き取り、
その切実な要望を受けて、被害の状況や再建に必要な漁具その他を支援しようと決めました。
; ?>/images/311/photo07.png” /></p>
<p>松島湾、三陸地方で古くから盛んな、ワカメやカキの養殖・アワビの採取・刺網漁に不可欠な小型の漁船は、津波によって少なくとも10,000隻が失われました。</p>
<p>急に発生した需要に、造船メーカーは生産が追いつかず、現在、漁船が手に入るのは数ヶ月から1年先という状態でした。</p>
<p>私たちは手に入りやすい中古船で状態の良いものを、国内の各地から手配することにしました。</p>
<p>また、アメリカと中国で、三陸仕様の和船を造船し、輸入もしました。</p>
<div class=)
; ?>/images/311/photo08.png” /></p>
<p><span class=) 9月4日の寄贈・進水式の様子。
9月4日の寄贈・進水式の様子。
漁船を受け取ったうちの一人、大友さんは
「みんな辛い思いをしているが、今回船が来てくれて、震災前に見たような『大漁の夢』が近づいてきました。」
と力強く語ってくださいました。
; ?>/images/311/photo09.png” /><br />
<span class=) 佐藤昭氏(塩竈市長) ビル・ホラン(OBI代表)
佐藤昭氏(塩竈市長) ビル・ホラン(OBI代表)
塩竈市浦戸諸島のカキ、海苔養殖や、刺し網の漁師のために、いち早く漁具の支援を行ったオペレーション・ブレッシングに対する塩竈市長からの感謝状を受ました。
震災前日の3月10日、浦戸諸島桂島に住民票を移し牡蠣生産者としてのスタートを切ろうとした矢先に被災した小泉善雅さんの、浦戸の漁業再生へのストーリーです。
; ?>/images/311/photo19.png” /></p>
<p>最近では養殖復興のサポートとして、宮城県気仙市の漁港にてホヤ養殖用の重り作りと養殖ロープの加工作業をお手伝いしています。</p>
<p>この日は牡蠣殻を70個程ロープに通していくという作業でした。この牡蠣殻にホヤの種苗が付き、海の中で成長していきます。<br />成長して出荷出来るまでに5年程かかるとの事ですが、その第一歩となる大事な作業です。</p>
<p>わざわざ東京から参加してくれた高校生ボランティアの方もいて、お陰で作業がスムーズに進みました。</p>
<h3>硯石運搬重機寄贈 2012年12月</h3>
<p class=)
; ?>/images/311/photo10.png” /></p>
<p class=) 600年の歴史を誇る雄勝硯。その産地である石巻市雄勝も津波により壊滅的な被害を受けました。
600年の歴史を誇る雄勝硯。その産地である石巻市雄勝も津波により壊滅的な被害を受けました。
雄勝の硯職人さんは、保有していたクローラキャリアを失い、震災後、採石した重い原石を加工場まで運搬することが出来ずにいました。
オペレーション・ブレッシングは、伝統ある雄勝硯産業の再起のために、雄勝硯生産販売協同組合に原石を運搬する為の重機「クローラキャリア」を寄贈しました。
心のケア 2012年3月-継続中
; ?>/images/311/photo11.png” /></p>
<p>震災で家族や住居を失い、心の傷を抱えている人が多く、心のケアを必要としています。</p>
<p>仮設住宅で暮らす人たちの心のケア講演会「心とからだを考える」を開催し、悲しみを癒す手助けをするための支援を実施しました。</p>
<h3>被災地の子供の心のケア 2013年8月-継続中</h3>
<p class=)
; ?>/images/311/photo12.png” /></p>
<p>被災地に住む子供たちの心のケアのために移動絵画教室、「あとえりほーぷ」を開催しました。</p>
<p>「あとえりほーぷ」のミッションは、絵を描くことを中心に活動し、子供達が抱えたストレスの緩和に務めることです。</p>
<p>その他に、歌って身体を動かす、リフレッシュするなど要素も取り入れて、子供たちが知らず知らずのうちに抱えたストレスの緩和に務めたいと思います。</p>
<p class=)
; ?>/images/311/photo13.png” /></p>
<p>絵画の他にも歌って身体を動かす、リフレッシュするなど要素も取り入れてます。</p>
<p>休憩時間にはおやつに手作りのワッフルを提供しました。</p>
<p><strong>ワッフル作りには近隣の方や海外からのボランティアに加え、「私も作りたーい」と小さなボランティアが活躍してくれました。</strong></p>
<p>最後には、<strong>「また、来てほしい!」と熱烈な声があがり、一緒に参加してくださったお母さんも笑顔でした。</strong></p>
<h3>パソコン教室</h3>
<p class=)
; ?>/images/311/photo14.png” /></p>
<p>私たちが被災地で支援活動を行う中、再就職のためにパソコンを覚えたいという声が多く聞かれました。</p>
<p><strong>そこで就業支援とコミュニケーションの場として</strong>パソコン教室を開催しました。</p>
<p>はじめは少し緊張気味だった参加者の皆さんも、時間が経つにつれてみるみる指の動きが滑らかになり、次々と新しいスキルに挑戦して行きました。</p>
<div id=)
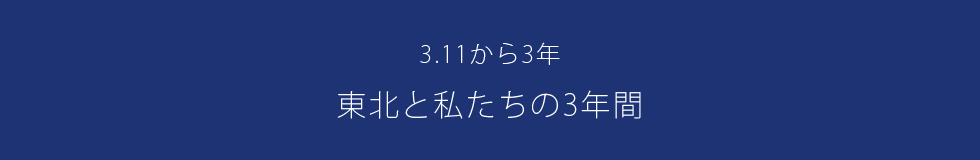
; ?>/images/311/photo15.png” /></p>
<p>福島では子どもたちが外での活動を控える自主規制のガイドラインとして、 「被爆線量 0.20 マイクロシーベルト以下」という基準があります。</p>
<p>いまでも、これ以上の数値は福島のあちこちで測定され、</p>
<p><strong>子どもたちの屋外での活動時間を自主的に制限せざるをえない 幼稚園や保育園がたくさんあります。</strong></p>
<div class=)
; ?>/images/311/photo16.png” /></p>
<p>外遊びが許された時間は、1日たったの30分という地域もあります。</p>
<p>福島原発の影響で自由を奪われている子どもたちに、思いっきり外で遊んでもらうために、移動用のバスを送りました。</p>
<p>子供たちはバスに乗って遠足へ出かけたり、外で思いっきり遊んだそうです。</p>
</div>
<h2 class=) 感謝の声
感謝の声
; ?>/images/311/voice01.png” /></p>
<p><img alt=)